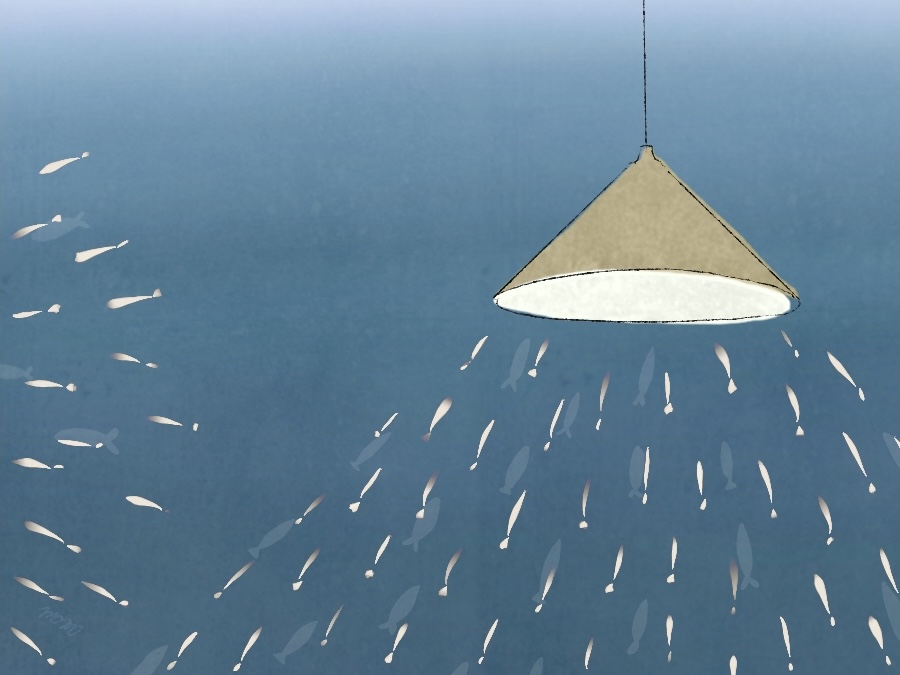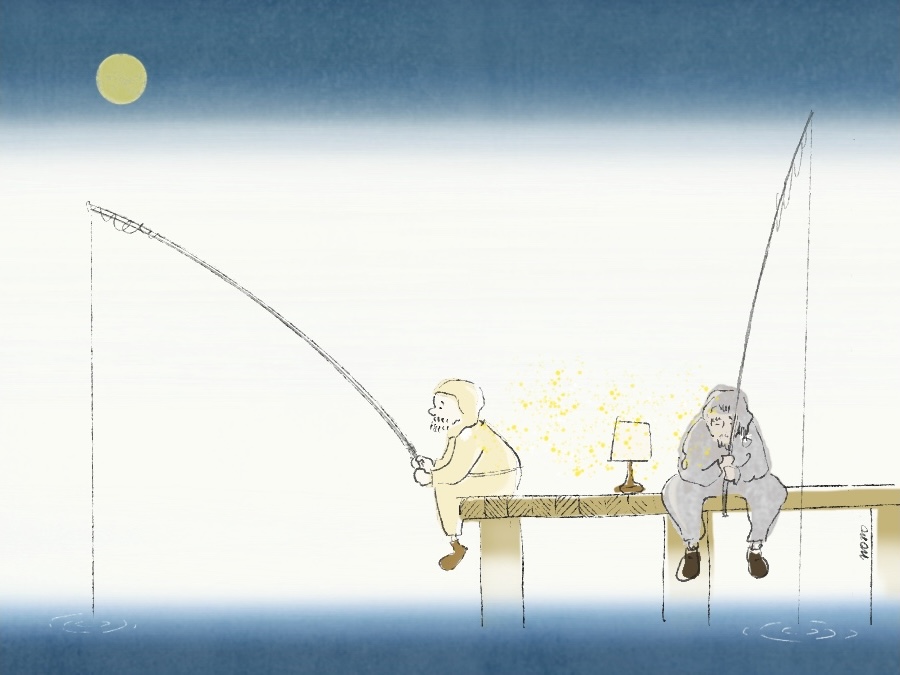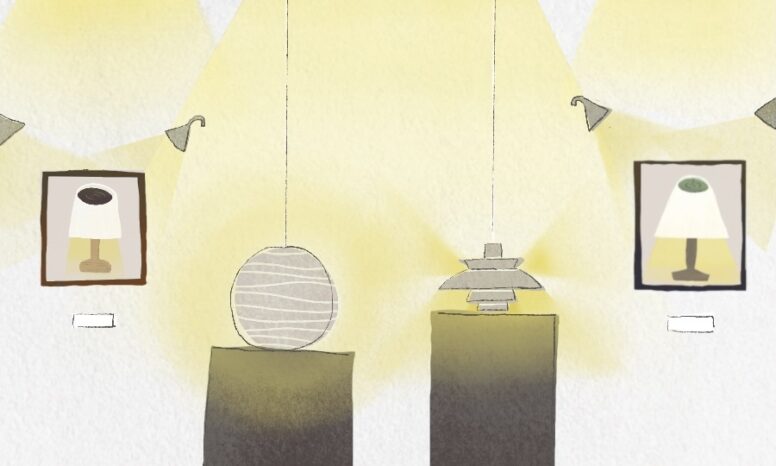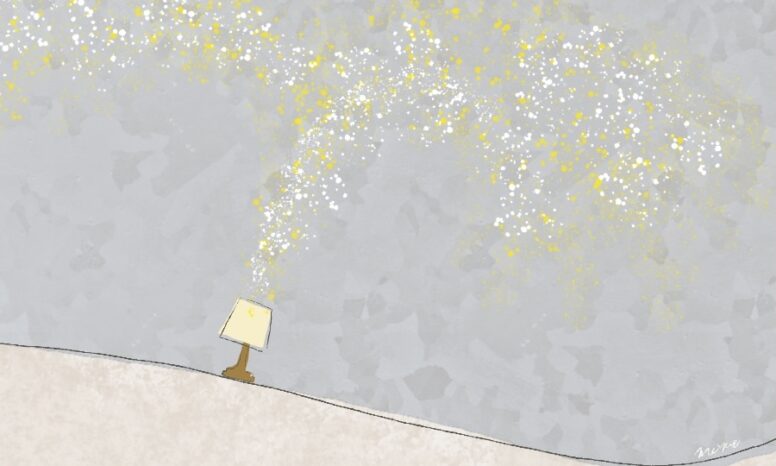陰翳礼讃を疑う

感動、関心
ひとりの人間
疑問、考察
ひとりの人間
感動、関心
ひとりの人間
疑問、考察
ひとりの人間

人柄と思想
照明の世界に入ると何はともあれこの作品を読むことになるでしょう。もしかしたら、業界内に限って言えば、同著の「春琴抄」や「痴人の愛」「細雪」を超える知名度かもしれません。それくらいに浸透している本です。
その美しい描写と日本人特有の着眼点は、海外においても評価され、日本人さえもはっとする表現はわたしたちの潜在的な美意識を掘り起こすような作品となっております。またタイトル通り、陰影にまつわる考察は、現代においても照明が語られる際にはよく取り上げられる部分です。
その内容は文明開花による西洋化への憂いにはじまり、あかりへの深い考察を中心に、暮らしに対する著者の思いと気付きが綴られているものです。随所に見られる美しい言葉の数々は読む人間を魅了する、まさに耽美派の筆頭たる表現力なのですが、随筆であるが故に溢れ出す著者の性質や、作内では語られない多くの背景もあるため、あくまでひとつの「作品」として読むことをお勧めします。
なぜこのようなことを言うかというと、あの谷崎の言うことだからきっとすごい、信じたい、という先入観がこの随筆を読む上では非常に邪魔なものになってくるからです。
谷崎潤一郎はもともとは並々ならぬ西洋趣味の人で、あまりの執心ぶりから崇拝とまで言われていたことは有名な話。関西への転居を機に、一転、日本の美意識に目覚めていくのですが、極端な言い回しや早計な物言いなどが多く、同氏に内在する偏屈と素直の交点座標が垣間見えてしまう作品でもあります。
そして、他作品では狂気を煮えたぎらせていたものの正体を見てしまったようでバツが悪いということもあり、実は谷崎潤一郎作品のファンであるほど、この作品の評価は低かったりします。もちろんきっかけがあって考えが変わることや、改めて気付くことなんかは誰しもあること。より古い随筆家の言葉を借りるならば「世の中にある人とすみかと、またかくのごとし」ですから、人というのはもう随分と昔からそうなのでしょう。


観念と現実

ここで、そんな谷崎潤一郎の一面を垣間見るエピソードを、秘書・和子さんが著書にて記されているので紹介します。谷崎潤一郎は後年、家を新築するのですが、その際に設計者にこのように言われます。
”陰翳礼讃を読んで先生の好みはよく知っている。必ず期待に添う家を作るから安心して欲しい”
それを受けて本人はなんと、感心するでもなく喜ぶでもなく、
”えらく不安になっちまった”と言います。そして、続いて”どうも困ったことになった、今からじゃあ断っても間に合わないかね”と、真顔で心配したという話。
この作品を執筆している当時は、西洋崇拝を経ての10年後。あらためて日本の文化に目を向けていた様相もありますが、その暮らしぶりといえば、同じく和子さんの談にあるように”実生活では何につけても極めてモダンで、清潔で、明るく近代的であることを望んでおられた”とのこと。
同著では十分に明るい昼でも灯りがずっと付けてあったという皮肉めいたことも書かれています。どの口がおっしゃるのかしら、とも聞こえてきそうなこのエピソードまでご存知の方は少ないようで。
ここで教わるのは「実際に生活している感覚」と、「言葉で語られる観念の美学」というものは全く違うこと。続いて、和子さんは”そんなことは誰しも往々にしてあり、もちろん谷崎潤一郎とて、例に漏れずその一人であった”とおっしゃっています。
陰翳礼讃は随筆として書かれていますが、その実「谷崎潤一郎」という感性が、生活の中に潜む気付きや様子を表現するとどうなるか、という表現に挑んだ作品だと感じています。和子さんの言葉からもわかるように「陰翳礼讃」というのは実は観念、そして美学の本。
一般家庭や日常が舞台となってはおりますが、盲信的に感化されるとまさかの本人からしっぺ返しを喰らうというなんとも溜飲が下がらない結果になります。とはいえ、美学の本と割り切りさえすれば、商業施設や公共の場所における照明の演出に活かせる感性の書と変容するのが実に面白いと、わたしなんかは思います。
そして、わたしたちのように暮らしのためのものをつくる人間に、”観念の美学”と”実生活”との「境界」というものに気付かせてくれるという意味では、たいへん学びのあるもの。
若かりし頃は、その繊細な表現と神妙な着眼点に心を奪われたものですが、自分が身を投じて分かる事があると思うと、改めて疑うという行為の大切さに気付きます。昔一度読んだという方も、これから初めて読むという方も、この機会に是非手に取ってみてはいかがでしょうか。