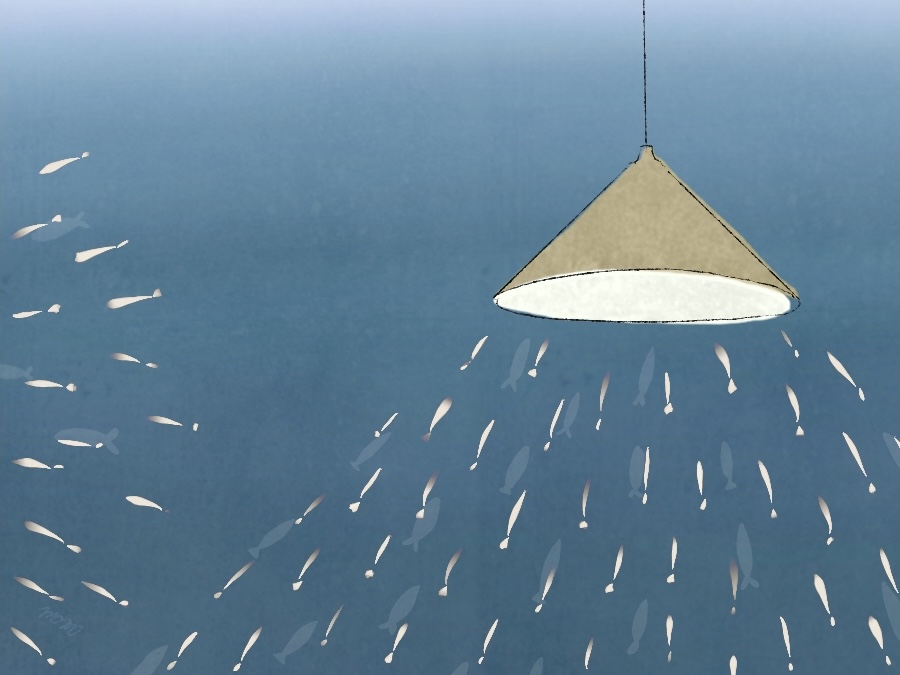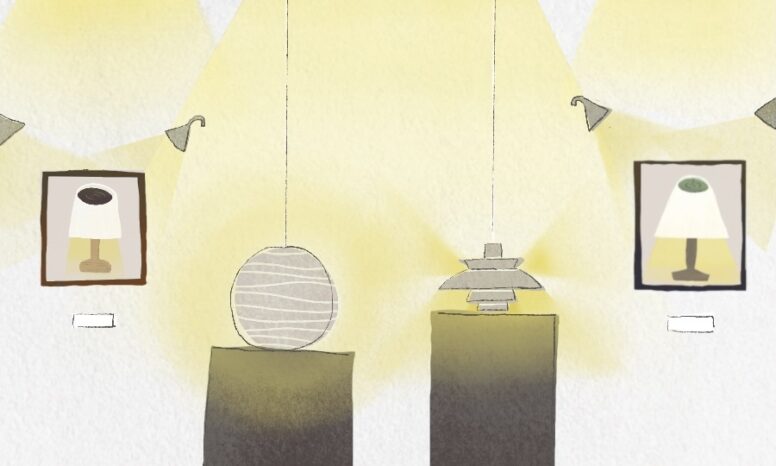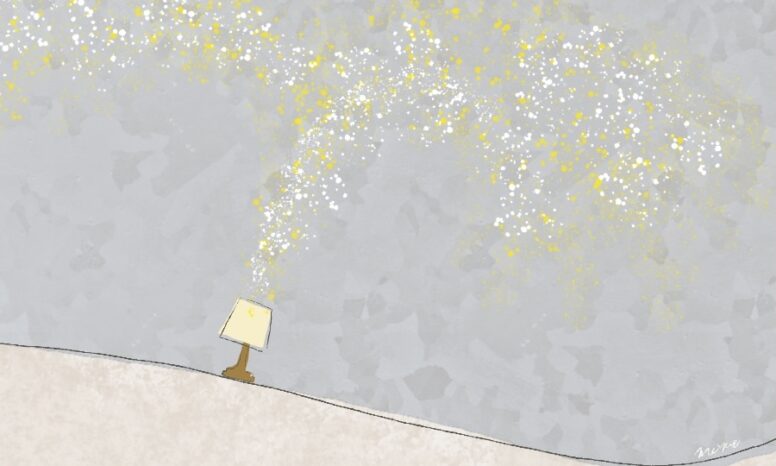聴竹居を訪ねる

トレンドを追いかけるだけの
海外様式の模倣を否定する一方で
伝統に縛られすぎる和のあり方も
同様にいさめた藤井厚二
その理想がここにある
トレンドを追いかけるだけの
海外様式の模倣を否定する一方で
伝統に縛られすぎる和のあり方も
同様にいさめた藤井厚二
その理想がここにある

住宅こそ
その国の
代表建築
みなさまは聴竹居(チョウチクキョ)という建築をご存知でしょうか?これは藤井厚二という設計士が建てた住宅で”日本の住宅の理想形“と言われているものです。「其の国の建築を代表するものは住宅建築である」という言葉の通り、彼は生涯を一般住宅の研究に捧げ、自ら住まいである聴竹居を完成させました。
通気性や耐震性など、日本の気候や風土を念頭にした構造、そして住む人が自然と共生出来る環境を実現。また90年以上前にも関わらず、椅子座様式や電気設備など、当時としては最新鋭の価値観と技術を盛り込んだ昭和におけるモダニズム建築の代表格として、重要文化財にも指定されています。
彼が活躍した1900年代というのは、西洋文化の流入が始まり、日本人の生活様式がどんどん欧米化していった時代。商業施設や公共の建築物に遅れをとる形で、一般住宅にもその影響が徐々に表れていきました。
新しい価値観、学ぶべき技術、構造、素材、そして気付かされた美意識などが多くの日本人を虜にする中、彼が憂いたのは、軽率な海外様式の模倣。その土地で育まれたものが、別の土地で同じパフォーマンスを発揮できるか。さらにそれを模倣しただけのものであれば、どちらの国のためでもないどっちつかずなものになってしまうでしょう。
大切なのは、改めて日本という土地を意識し、そこにローカライズする事。そういう理念のもと、建てられた「聴竹居」は、見事なまでに和と洋が融合しています。
この考え方を知った時、大変僭越ながらわたしたち「はく」の思いとの相似を感じ、深い納得と感銘を受けました。
ところで、日本で最も売れているにも関わらず、ある方面から散々叩かれている白くて薄いシーリングライト。通称「シロモチ」。お部屋をおしゃれにするにはまずこれをやめて、ペンダントやスポット型のシーリングにせよなど、さまざまな提案が飛び交うのですが、実はこの「聴竹居」にもしっかり採用されているのです。
というのも、これこそ日本の暮らしを念頭に作られた照明だから。狭くて天井が低い住宅で、一室一灯の文化が育ち、明るさを好むわたしたち。他国にいってこの製品をみることはなかなかありません。


ガラスの傘に
裸電球が
最も不満な
照明である

日本はトレンドやスタイルの変化が目まぐるしく、他国への憧れも強いため、自国のスタンダードを軽視しがち。特に照明の世界では、北欧を模倣するスタイルがなんとなく“分かっている”感じもあるためブランディングとして使われやすいのですが、一面的なそれは正に軽率な模倣。ライフスタイルに合っているものをわざわざ取り替えましょうというのは、アドバイスとも違うように感じます。とはいえ、そんなふうに言われてしまうには理由が二つあります。
まず一つ目は「意匠」が悪いから。分かりやすくいうと見た目が良くないからです。よく売れる事で価格競争に飲み込まれているほか、デザインを施す部分が極めて少ないという事がそれを助長しています。
そして二つ目は、最大光量がうたい文句になっているから。これは車で言えば最高速度300km出ます!と言っているのと同じ。
これが照明のもたらす効果の本懐ではないのですが、大は小を兼ねるという意識も強く(それ自体は悪いことではありません)、効果的な使い方も浸透していないため、使用者は調光や調色をあまり使わずON(最大)-OFF(消灯)のみに終始しがちです。
このようにライフスタイルとしては適切な機能を持たされているはずが、それ以外の要素が“おしゃれ”や“丁寧”とかけ離れているため、コーディネートから除外されるというのが彼らの今の宿命。それでも一般市場で売れているということが、多くの日本人が適切なものであると判断している証拠でしょう。
あとは製造技術を持ったメーカーが意匠の重要性に気付いて着手するのみ。ダウンライトのことを思えば、意匠に注力するシロはあるので時間の問題かなとは思います。
ともかく、使い方さえ分かれば日本のライフスタイルにあった器具。頭ごなしに否定し、一新してしまうのではなく、上手く使う方法を伝える事こそ専門家やコーディネーターのすべき事だとわたしたちは考えています。
話を戻して、今より90年以上も前にこのスタイルがわれわれにとって最適であると明示した藤井厚二氏の考察と検証結果の精度の高さには脱帽です。もしかしたら、この“シロモチ”を企画した方も、当初はわたしたちと同じように同氏に感銘を受けて開発したのかもしれません。
このように古きを知ることで、今語れること、そして判断できることは多分に増えます。
みなさまも是非一度、聴竹居に足をお運びください。